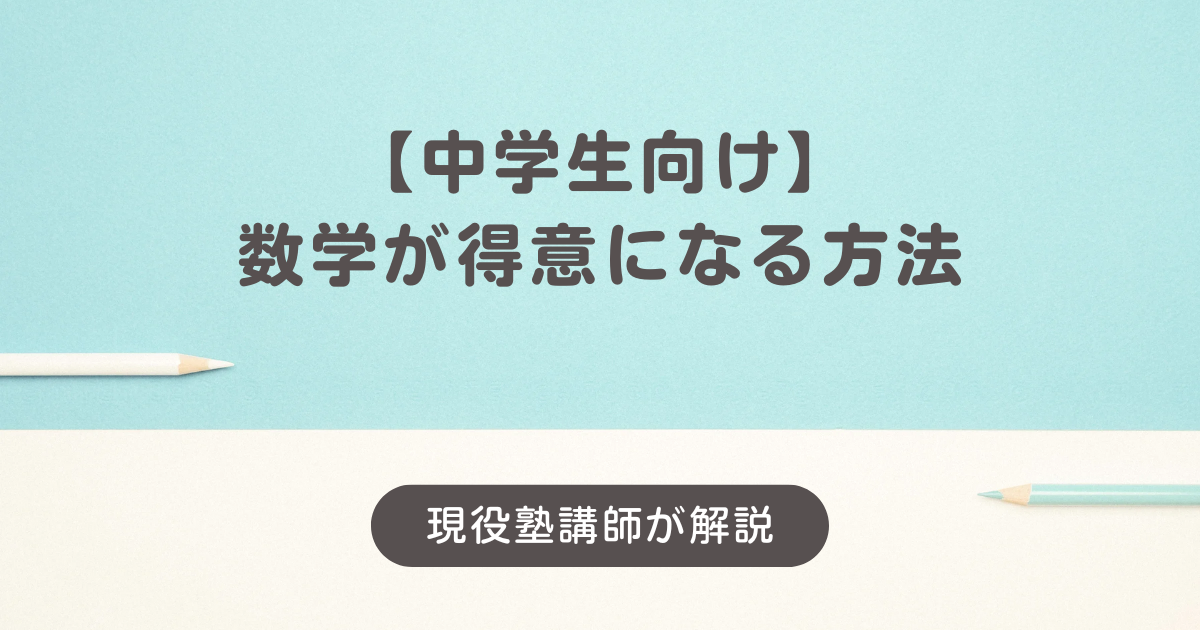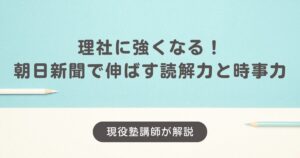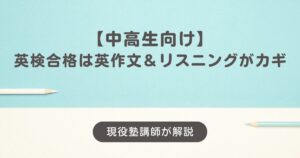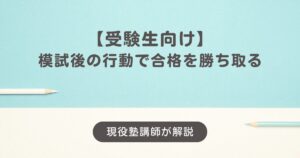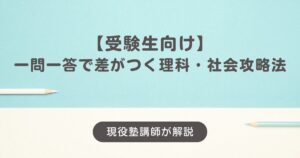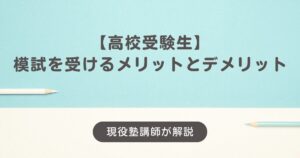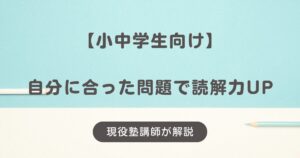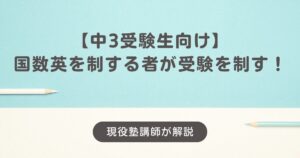数感覚とは、数字や量を直感的に理解する力で、文字式・方程式・比例・関数・図形・文章題など、あらゆる数学の基礎となります。
さらに、問題文を正しく読み解く読解力や、計算力が組み合わさることで、初めて数学が得意になれるのです。
中学に進学すると、算数はできていたのに数学が急に難しく感じる…と悩む子どもは少なくありません。
その原因は、単なる計算力の不足だけではなく、「数感覚」と「読解力」の不足が関係しています。
 きぃ先生
きぃ先生数感覚+読解力+計算力をバランスよく鍛えれば、数学は苦手科目から得意科目に変わります。
日々の学習に少しずつ取り入れることで、着実に理解力と自信を伸ばせます。
この記事でわかること
- 中学数学が急に難しく感じる理由と、算数との違い
- 数感覚・計算力・読解力が数学の理解に与える影響を知ることができる
- つまずきやすい単元ごとの具体的な勉強法とおすすめ教材
目次
中学数学が「急に難しく感じる」本当の理由
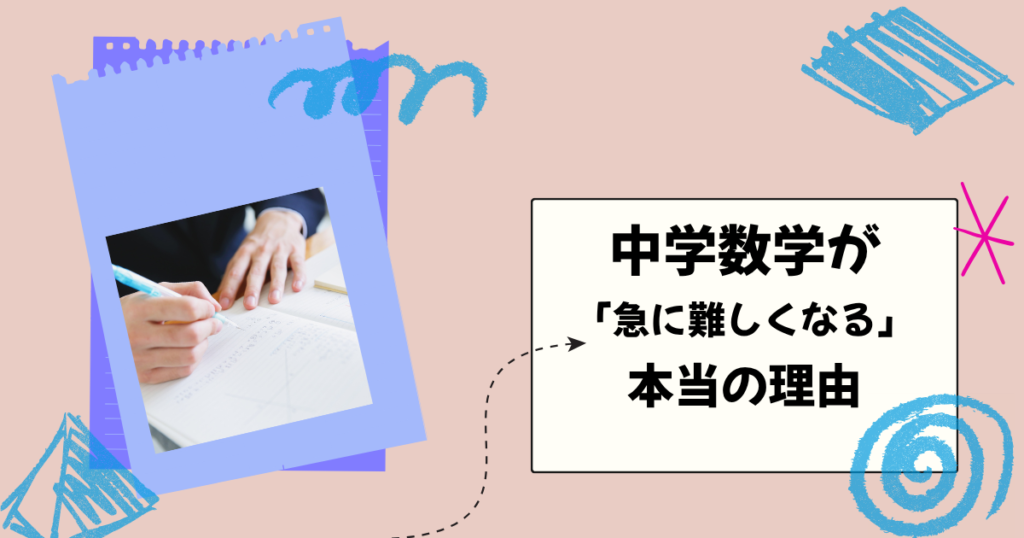
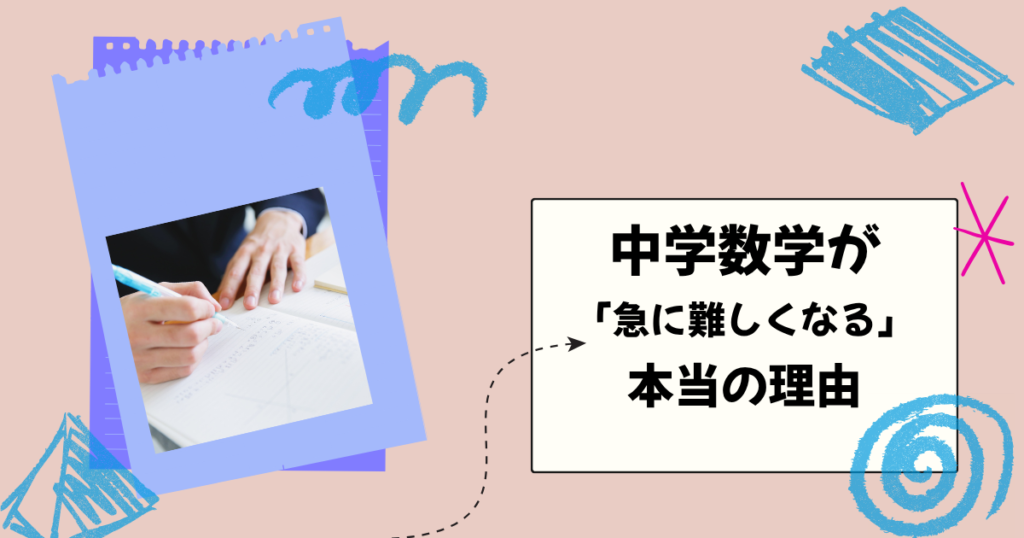
算数と数学の決定的な違い
小学校の算数は「具体的な計算」が中心。
でも中学の数学は、「数字の意味」や「関係性」を理解することが求められます。
たとえば、算数の「5+3」は具体的な数。
でも数学の「x+3=5」は「何に3を足せば5になるか?」という関係性の理解です。
「計算できるのに解けない」3つの理由
- 抽象的な文字(x、y)の理解が難しい
- 数の変化や関係をイメージできない
- 長い文章問題を読み解く読解力が必要
数感覚があると
- 計算の見直しが早くできる
- 問題の意味がすぐにイメージできる
- 関数や図形の変化を直感で理解できる
数感覚ってどんな力?【具体例】



「数感覚」=数字の大きさや関係性を直感で理解する力になります。
- 「50%OFFって半額だよね」:割合の感覚
- 「3分の1はだいたいこれくらい」:分数の大きさの感覚
- 「y=2xは、xが2倍ならyも2倍になる」:関数の変化の感覚
数感覚だけじゃない!計算力・読解力もカギ
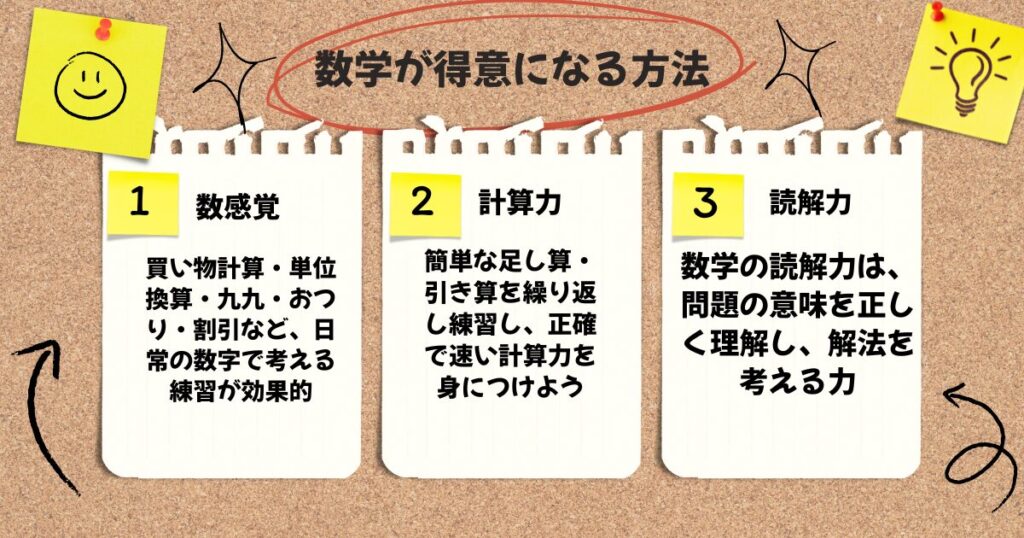
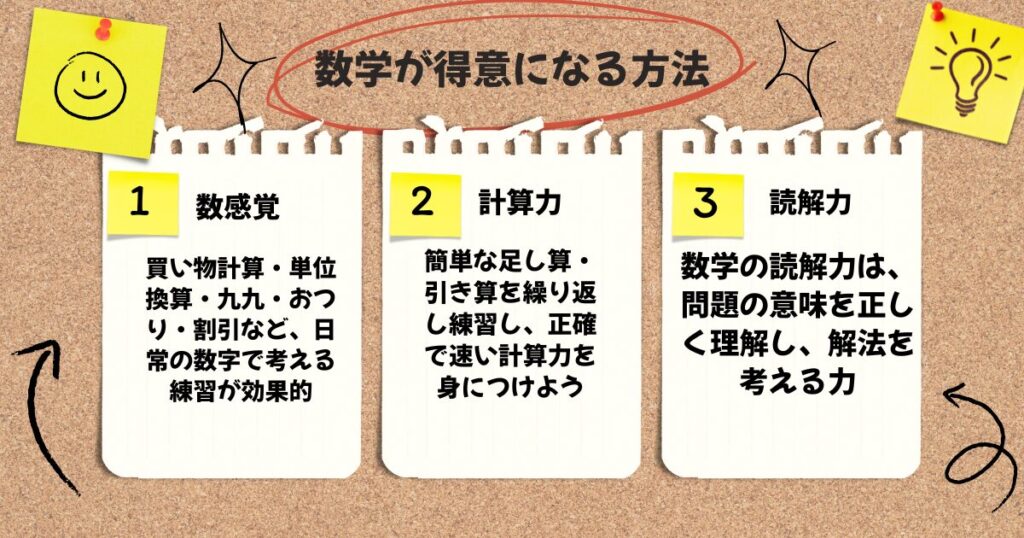
【数感覚】が弱いと



式を作る力・問題の構造を理解する力が弱くなる。
- 数の意味がイメージできない:式の意味がわからない
- 符号(+−)や割合、比例・反比例が直感的に理解できない
- 覚えた公式や手順が「なぜそうなるか」わからないので、忘れやすい・応用ができない
【計算力】が弱いと



理解していても「正解」につながらない。自信をなくしやすい。
- 計算ミスが多発し、正解までたどり着けない
- 頭の中で簡単な計算ができないと、途中式が複雑になって混乱
- 「わかっているのに点数が取れない」状態になる
【読解力】が弱いと



「数学的な言葉の読み解き」ができず、応用・文章問題でつまず。
- 文章問題の意味が読み取れない
- 「何を聞かれているのか」がわからず、式が立てられない
- 図形や関数の問題文の条件を取りこぼすと間違える
- 数感覚=数の意味をイメージする力
- 計算力=正確に処理する力
- 読解力=問題文を読み解く力



この3つがバランスよく育っていないと、理解・正解・応用のどこかで必ずつまずきます。
数学に必要な「読解力」とは?
なぜ読解力が必要?



数学は「言葉で数字の関係を伝えてくる教科」
問題文を正確に読み取らないと、式が立てられません。
\読解力を伸ばす方法を解説/
きぃ先生のまなび家

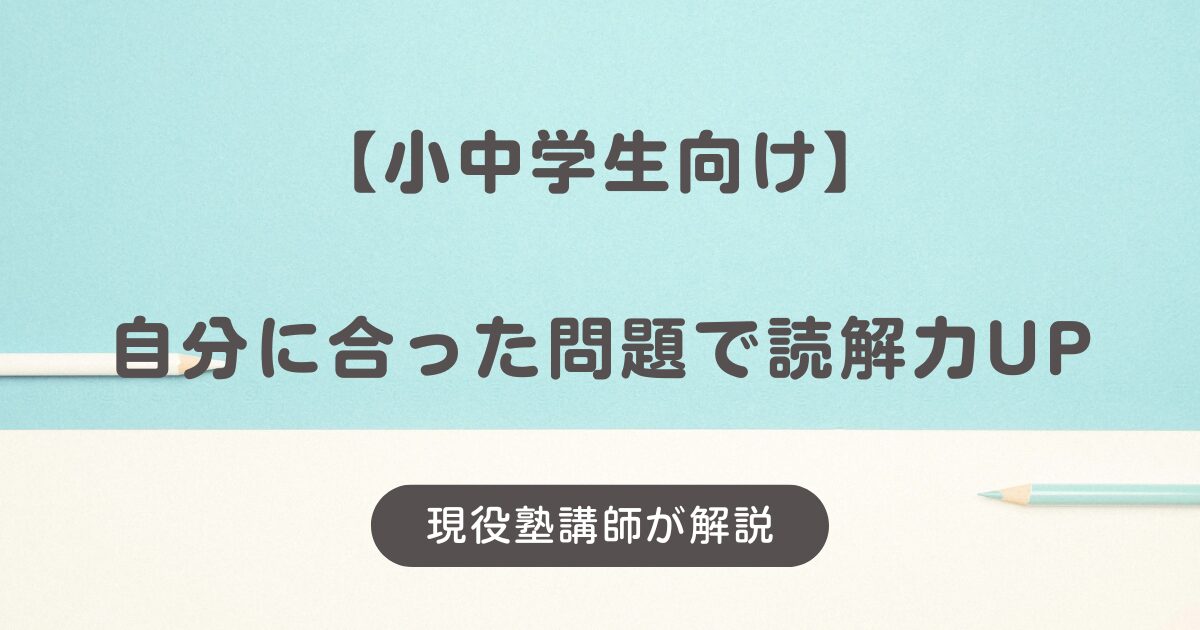
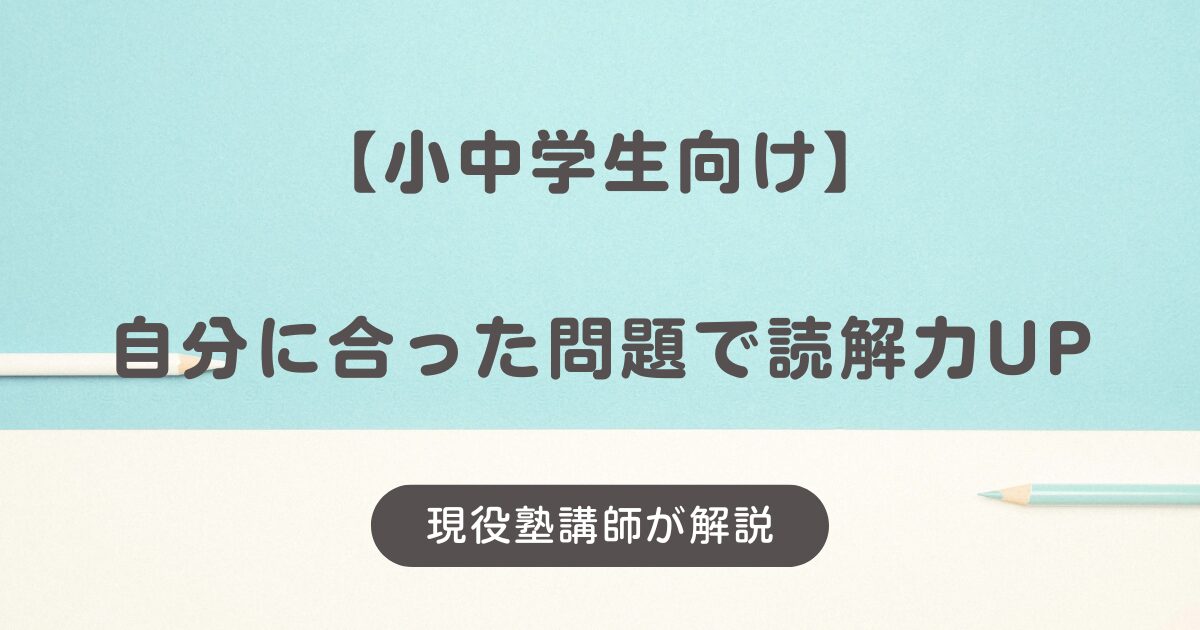
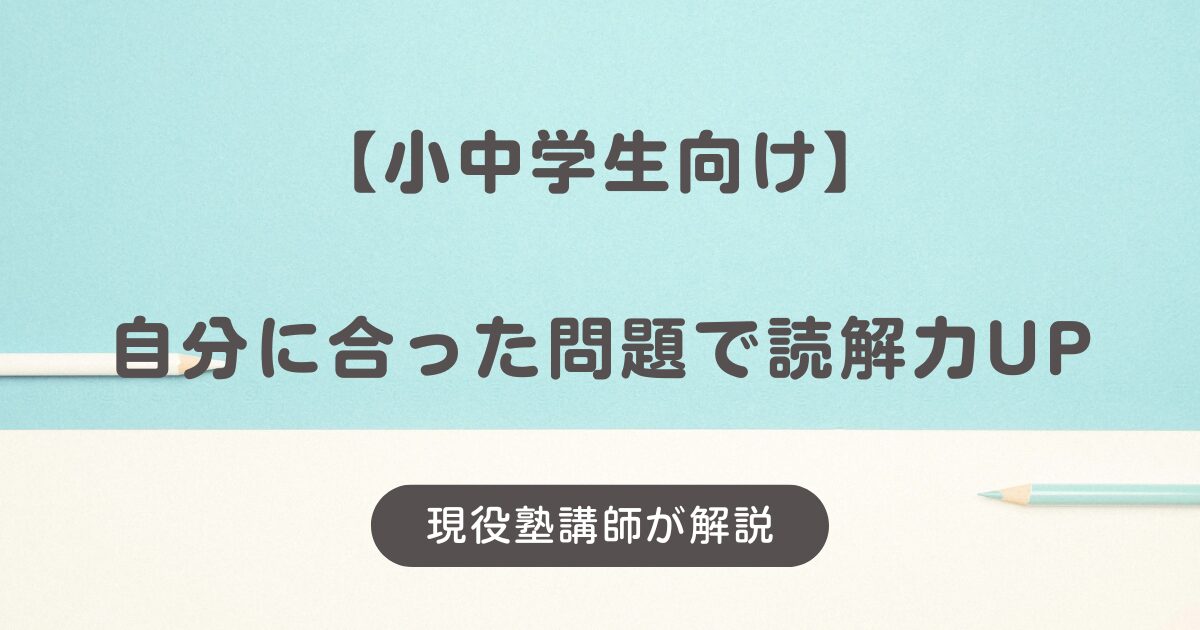
【中学生】読解力を上げる勉強法と苦手克服の秘訣とは? | きぃ先生のまなび家
読解力は、すべての教科の基礎となる重要な力ですが、いきなり難しい問題に取り組むと挫折しやすくなります。効率よく力を伸ばすには、スモールステップで少しずつ積み上げ…
中学生がつまずきやすい単元と「数感覚」の関係
文字式・方程式
- 「xってなに?」→具体的な数から文字への変換ができないとつまずく
→「2+3=5」→「x+3=5(x=2)」の流れで理解する練習が効果的
比例・関数
- 「xが増えたらyがどう変わる?」の感覚がない
→表を作って、数字の変化を目で見てから、グラフで線の意味をつかむ
図形の面積・体積
- 公式を暗記しても、形の構造を理解していないとミスが増える
→実際に図を描き、分解や組み立てをして学ぶのが効果的
文章題
- 条件が多く、何を聞かれているのか読み解けない



数感覚と同時に、問題文を読み解く力(読解力)も必要です。
【完全版】計算力強化法+数感覚を育てる勉強法
計算力も筋トレ:おすすめ問題集
\毎日10分でOK!/
リンク
\基礎固め【計算編】/
リンク
\基礎固め【関数・図形編】/
リンク
文字式は「具体→抽象」で理解
- 「2+3=5」を「x+3=5」に置き換える練習
- 最初は数字で考え、徐々に文字に慣れる
比例・関数は「表とグラフ」で視覚化
- xとyの表を作り、どう増えるかを確認
- その表からグラフを書き、線の傾きを理解する
図形は「描く・分解・組み立て」
- 方眼ノートに正確な図を描く
- 複雑な形は、長方形や三角形に分けて面積を計算
- 展開図や立体も描いて、立体感を養う
日常の数字でトレーニング
- 買い物で「30%OFFはどれくらい安い?」を考える
- 地図を見て「距離と時間」の計算をする
- ゲームのダメージ計算や確率も、良いトレーニング
まとめ:数感覚+読解力+計算力=数学が得意になる
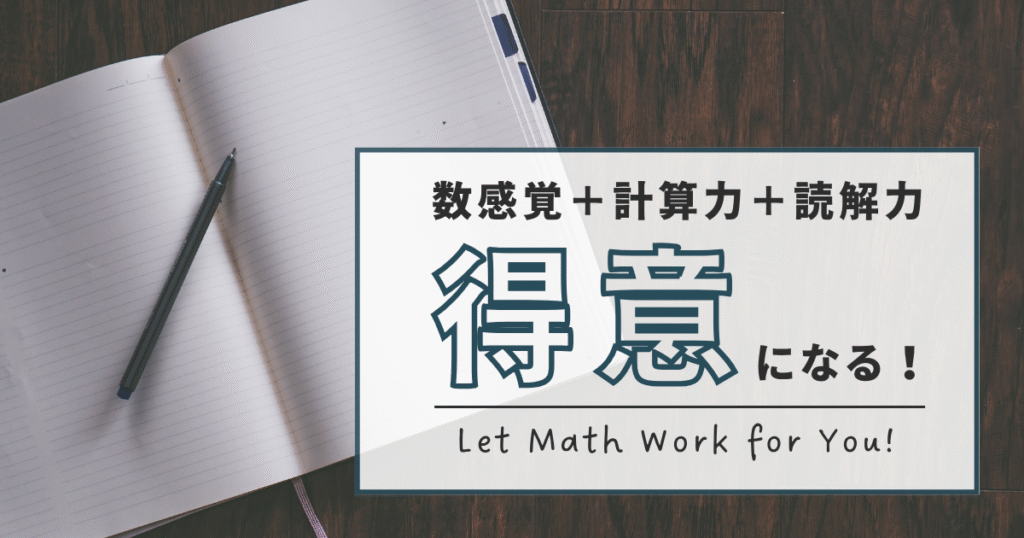
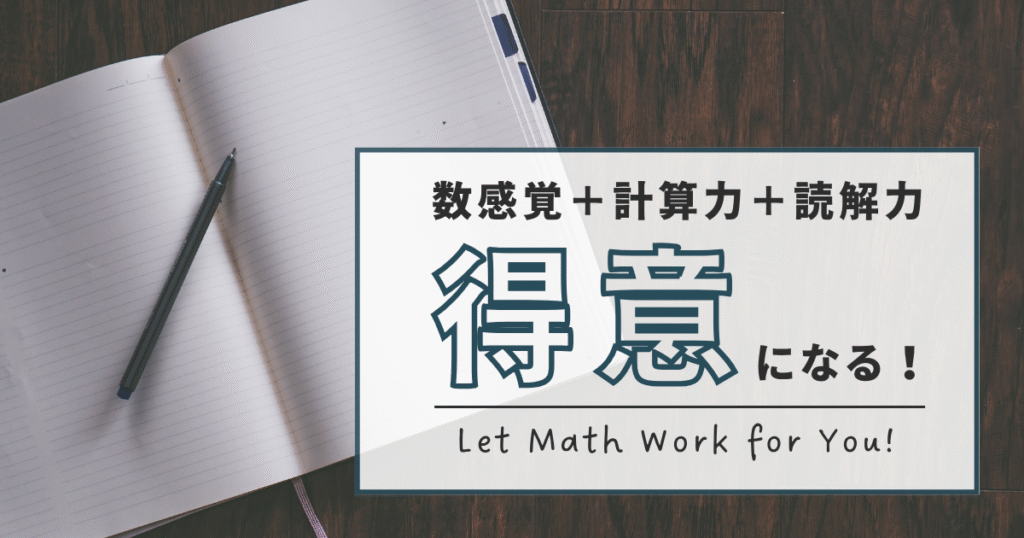
数感覚・計算力・読解力が理解のカギ
- 中学数学が難しく感じるのは、小学校算数との考え方の違いや基礎力不足が原因
- 数感覚・計算力・読解力がそろうことで、数学の理解がスムーズになる
- 単元ごとの勉強法と教材を工夫すれば、つまずきを克服して成績アップにつながる